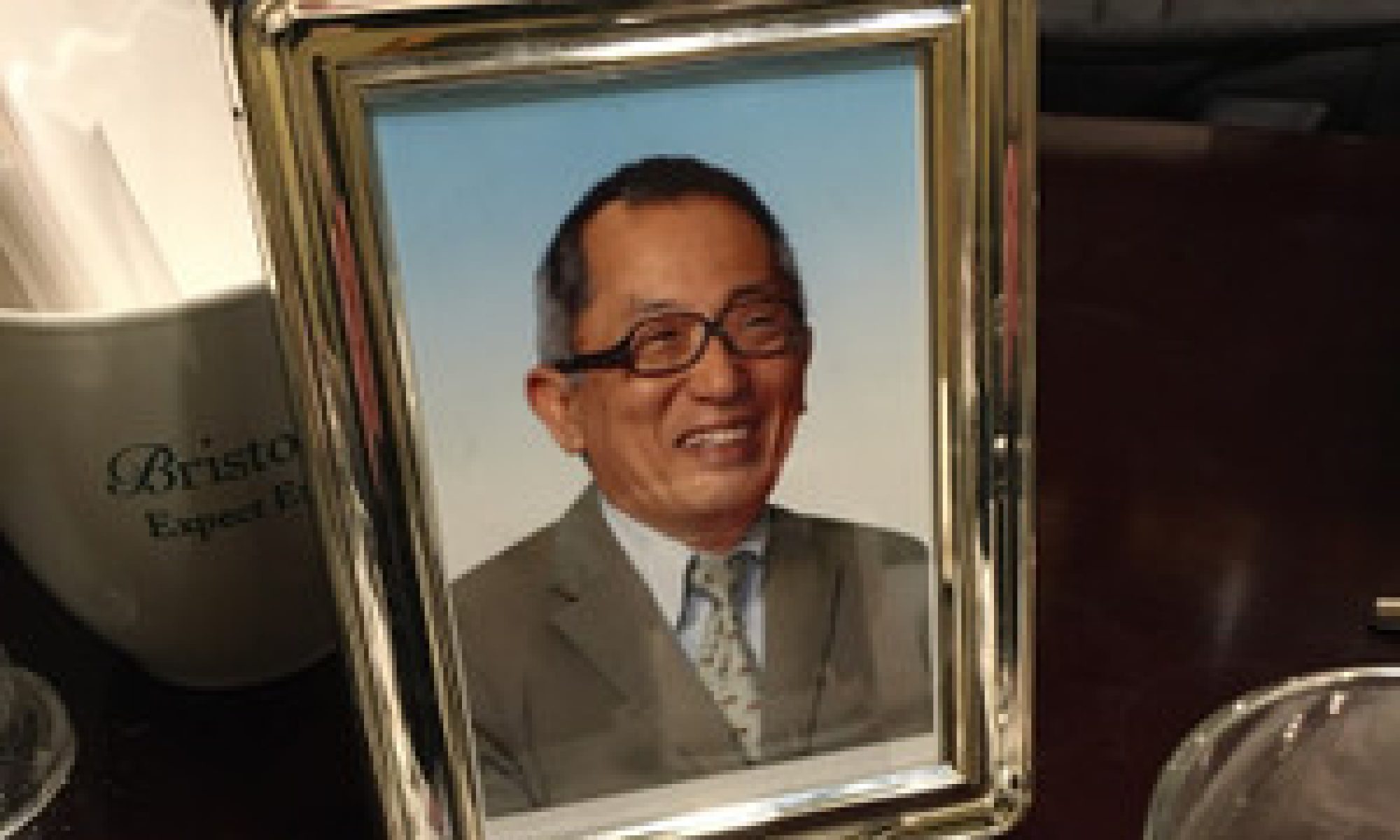2010年3月16日
出版物のネット配信のアプローチにはいろいろありそうである。ひとつは比較的著作権などの話し合いがしやすい学術書を配信するアプローチもあるだろう。しかし、出版物といっても書籍ではなく新聞が配信されるとどうなるのだろう?
メディアを比較してみるとき、そのメディアの持つ時間のサイクルで見るというのも見方のひとつである。たとえば書籍は不定期でそのサイクルは長い。作家をブランドとして見ると一人の作家が書籍をリリースするサイクルは幾ら短くても一ヶ月以上かかるだろうし、寡作な作家の場合は数年に一冊のペースだろう。
年鑑という出版物もある。このサイクルは一年でる。季刊というカテゴリーは四半期ごとである。月刊は毎月、週刊は毎週でこのあたりは雑誌というカテゴリーになる。更に短くなると日刊でありこれが新聞のカテゴリーである。
これよりも短くなると電波メディアになり、ラジオ、テレビと言うメディアが時間を単位にして番組を流している。これらはすべて発信側がその時間の軸を決めている。
ところがインターネットは言って見れば瞬間メディアである。それと同時に蓄積もできることから書籍的性格も持っている。
面白いことはインターネット上ではこれまでのメディアのもっていた時間軸をすべて再現できることである。さて、そこで新聞を見てみよう。
新聞は毎日発行されているわけだが、そこには独特の定期購読という仕組みがあって毎朝あるいは毎夕家にまで配達されるのが基本になっている。
したがって、読者はいったん購読契約をするとその契約に従って毎日同じ新聞を読んでいる。たまに駅のキオスクでほかの新聞を見ることもあるだろうが基本はすべて同じ新聞を毎日見ている。新聞の購読契約は新聞販売店の販売員によって個別に家を訪問し購読契約を獲得して発行部数を構成している。アウトバウンドセールスである。したがってある新聞がどれだけの部数が売れるか、というのは販売店の組織の大きさに大きく依存している。販売店網が大きな新聞社の新聞はたくさん売れ、小さな新聞社はそれなりの部数しか売れない。
ところが、これがネットの配信となったとたん、これまでのアウトバウンドセールスであった新聞と言う商品はインバウンドセールスに変わる。
しかもリアル店舗を使うインバウンドセールスではその商品を扱っている店舗の数がインバウンドセールスの売り上げに関係するがネットの場合は販売店はひとつであるから、ネット上で販売店を幾ら増やしても同じ商品で同じ価格であれば販売店の数の意味はなく、実質的に販売店は一箇所となる。つまり、新聞がネット販売化されるともはや新聞の売り上げ部数は販売店網の大きさに依存しなくなってしまう。
それでは購読数は何できまるのか?購読者の最大公約数が持っている関心事に対して的確な情報を提供する新聞が最大の購読者を獲得する、といえるのではなかろうか?さらに、これまでは新聞社が販売店に新聞を配送するというプッシュ型のビジネスであった。ところがネットで配信するとなるとプッシュ型からプル型にビジネスの形が変わる。つまり、これまではセールス主体のビジネスであったものがマーケティング主体のビジネスに変わる。
それに従い、インセンティブも従来の洗濯石鹸とか自転車と言う拡販材料から潜在購読者を引き寄せるための何かに変化する。
どうも新聞の電子配信は単に紙でなくなるだけでなく、ビジネスのモデルも大きく変わるし、新聞社が販売店を通じて提供する、と言う形から購読者が読み比べて選択する、と言う形に変わる。
その結果はどうなるかわからないが、強力な販売店網を駆使して大部数を獲得していたところが部数を減らし、今までは販売網が弱かったために部数を獲得できなかったところがその内容の個性によって大きく電子部数を伸ばす可能性を秘めている。そんな変化がすぐ目の前に来ているのでは?